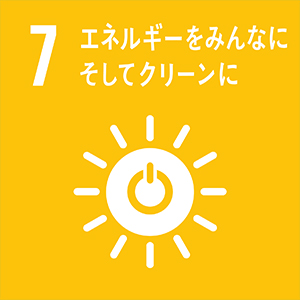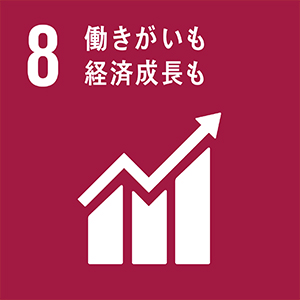一般財団法人 沖縄県環境科学センター
一般財団法人 沖縄県環境科学センター
SDGs(持続可能な開発目標)とは?
2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っています。SDGsは普遍的なものであり、弊社は積極的に取り組んでいます。

- 沖縄県環境科学センターのSDGsの取り組み
- 一般財団法人沖縄県環境科学センターは、1981年の設立以来、「健康の保持増進に必要な食品・飲料水等並びに生活環境の保全及び管理に関し必要な検査、調査研究、啓発等を行い、もって地域社会の健全な発展に寄与すること」を目的として事業を行っており、これはSDGsの取り組みにほかなりません。弊社のSDGsの取り組みと今後の計画を以下に記します。
有害化学物質、並びに大気、水質及び土壌の汚染については、現状を正確に調査・解析することにより、汚染の原因を突き止め浄化・改善に貢献します。水系感染症及びその他の感染症、感染性及び非感染性疾患、安全ではない水と公衆衛生及び衛生知識不足については、食品及び水道関連事業において、飲食に関わる調査・分析、及び衛生指導を引き続き行うことにより、人々の健康的な生活を確保し福祉を促進します。
質の高い技術教育・職業教育、持続可能な開発のための教育については、弊社の技術者による一般向けの講演や環境分野の出前講座、研修生の受け入れをさらに積極的に実施し、生涯学習の機会を促進します。また、島嶼県沖縄として、東南アジアや大洋州などの島嶼国からの実習生に対して、自然環境保全、生活環境保全及び公衆衛生に関わる研修を引き続き行うことにより、人材育成を図ります。
安全で安価な飲料水については、引き続き県内全域の上水の検査を行います。排水処理や再生利用については、産学官連携で実施している安価で高効率な排水処理の研究開発を加速させます。水と衛生については、事業者に対する衛生指導を強化します。水に関連する生態系の保護、回復については、河川やサンゴ礁域における自然再生事業を継続して実施します。以上より、水と衛生の持続可能な管理を確保します。
再生可能エネルギーについては、旧制度から取り組みを続けているJ-クレジット制度の普及啓発に努めます。エネルギー効率の改善については、弊社が手がけているエネルギー効率の改善につながる設備更新の促進事業を引き続き実施します。また、島嶼県沖縄として、東南アジアや大洋州などの島嶼国のインフラ整備につながる技術研究開発に挑み、持続可能な近代的エネルギーへのアクセスに貢献します。
適切な雇用、働きがいのある人間らしい仕事については、弊社は仕事と生活の調和に積極的に取り組んでおり、『沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業』として認証登録されています。経済成長と環境悪化の分断、持続可能な観光については、サンゴ礁保全、自然再生、観光振興をテーマに離島や観光地において、次に繋がるモデルケースの創出に取り組んでおり、持続可能な経済成長とディーセント・ワークを促進します。
持続可能な産業化、雇用については、産学官による研究開発の結果、バイオレメディエーション分野で雇用を創出しています。クリーン技術、環境配慮技術・産業プロセス、官民研究開発、科学研究促進、技術能力向上については、微生物による排水処理・土壌浄化、サンゴの養殖・移植、オニヒトデ駆除など、引き続き産学官による研究開発を続けることにより、持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図ります。
公共交通機関の拡大、持続可能な輸送システムについては、エコ通勤に関する意識が高く、取り組みを自主的・積極的に推進している事業所として、弊社は『エコ通勤優良事業所』に認証登録されています。自然遺産については、沖縄県初の登録を目指して、官民一体で進めています。廃棄物管理については、処理・処分場の検査を通して環境上の悪影響の軽減に努めています。以上より、持続可能な都及び人間居住を実現します。
天然資源の持続可能な管理・効率的利用、持続可能な開発・自然と調和したライフスタイルについては、多様な地球温暖化防止事業を通して持続可能な社会を構築します。食料廃棄と収穫後損失については、弊社が手がける衛生管理指導・検査により、食品ロスを減少させます。(有害)廃棄物の発生抑制と適正管理については、処理・処分場の検査を通して実施します。以上より、持続可能な生産消費形態を確保します。
気候変動対策に関わる教育、啓発については、弊社が手がける地球温暖化防止実行計画やJ-クレジット制度、カーボン・オフセット、樹木によるCO2吸収、海域環境保全などの事業を通して、イベントにおけるブース出展や出前講座、環境関連講演会・セミナー・シンポジウムの講師、ODA関連事業における海外研修員に対する講義などにより普及・啓発し、気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じます。
海洋ごみや富栄養化については、陸域の赤土流出防止や自然再生事業を通して負荷低減に努めます。海洋及び沿岸生態系の回復については、サンゴ再生・栽培事業、オニヒトデ対策事業、ジュゴン保護対策事業などを通して回復に努めます。海洋・水産資源の保全、漁業、水産養殖、観光の持続可能な利用・管理については、サンゴ礁保全再生事業や養殖場の海域調査を通して、持続可能な開発に貢献します。
陸域・山地生態系、内陸淡水生態系、森林に関わる持続可能な利用については、ダムを含む淡水域の生物・水質調査事業を通して、生態系の保全に努めます。絶滅危惧種の保護、外来種の侵入防止、駆除、根絶については、生物多様性、ノグチゲラ調査、及び、マングース、ヒアリ、ツルヒヨドリなどの特定外来生物対策事業を通して、陸域生態系の保護・回復、及び生物多様性の損失の阻止に努めます。
効果的な公的、官民、市民社会などのさまざまなパートナーシップについては、県内外、国内外の研究機関や企業とのコンソーシアムによる事業を通して持続可能な開発のための実施手段を強化し、科学技術イノベーションの基盤を築いています。これからは、グローバル・パートナーシップを活性化することにより、沖縄で培った技術を類似した自然環境、気候帯の東南アジアや大洋州などの島嶼国に対して技術移転します。
これまでのSDGsの取り組み一覧
〜沖環科SDGsプロジェクト〜
-
- 2021/05/12
- 5/11(火)に、恩納村の赤土流出防止対策の活動に参加してきました!
-
- 2021/03/19
- 2020年度沖環科SDGsレポートを公開します。
-
- 2021/01/12
- 12/15(火)に、那覇市内のホテルで手洗い講習を行いました!
-
- 2020/12/08
- 11/11(水)に、向陽高等学校で食品ロスに関する出前講座を行いました!
-
- 2020/10/21
- 10/9(金)に、東風平中学校にて「職業人講話」を行いました!
-
- 2020/08/31
- 8/12(水)にマリエールオークパインにて手洗い講習を行いました!
-
- 2020/07/31
- 7/16(木)にパレットくもじにて手洗い講習を行いました!
-
- 2020/07/08
- SDGsプロジェクトにて、7/2(木)に那覇市内のホテルで手洗い講習を行いました!
-
- 2020/06/04
- 当法人で、野菜とイチゴのフードロスに関する取り組みを行いました!
-
- 2020/05/20
- SDGsプロジェクトにて、4/14(火)に当法人で手洗い講習を行いました!
-
- 2020/04/01
- 令和2年度より「SDGs事業実行班」の活動がスタートしました。
-
- 2020/03/25
- 3/24(火)に、「おきなわSDGsパートナー登録証交付式」へ参加しました!
-
- 2020/03/13
- 当センターは「おきなわSDGsパートナー」に登録されました
-
- 2019/03/25
- 沖縄県環境科学センターのSDGsの取り組み