
POINT 01認証取得前から
取得後までの徹底サポート
皆様の「お困りごと」を丁寧にヒアリングさせていただき、客観的に課題を洗い出します。その上で、課題解決につながる道筋をご提案いたします。また、継続的な運用や無理のない仕組み作りのための従業員教育として、座学をはじめ、ワークショップ形式、現場でのOJT方式等、ご要望に応じた対応が可能です。

HACCPに沿った衛生管理の
実現で食品等事業者様の
販路拡大へ
むけて徹底サポートします

\詳しく知りたい方は/
お問い合わせはコチラから食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去または低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。

※写真はイメージです
日本の食料自給率は約4割に留まっています(※1)。つまり約6割の食料を輸入に頼っており、輸入食品の安全性確保は非常に重要な課題となっています。そのため、輸出国に対し食品の衛生管理手法であるHACCPを求めていくためには、貿易上の透明性を確保する観点から、国内生産の食品においてもHACCPによる管理が必要とされています。
※1 カロリーベースで38%(令和3年度 -農水省-)
日本再興戦略(Japan is Back)において、日本の食品の安全・安心を世界に発信するため、海外安全基準に対応するHACCPシステムの普及を図る観点から、マニュアル作成や輸出HACCP支援のための体制整備を実施することが決定されています。沖縄はアジアのハブ拠点重要地区であることから、海外進出は企業の成長発展へとつながります。その際にはHACCPは必要不可欠となります。このようなことから、HACCPへの取り組みが求められています。
HACCPに沿った衛生管理では、「見える化」が重要なポイントで、「マニュアル」や「記録」の作成が必要となります。これまで経験や勘で培われてきた作業内容を「マニュアルに落とし込む」ことで、ベテランから新人まで誰の作業でも同様のレベルで実施できることが可能となります。また、チェックした内容を記録に残すことは「自分たちの身を守る財産」となります。難しく考えず、先ずは製造現場で行っていることを文字や写真などに起こしてみることからはじめましょう。
HACCPを導入するために、お金や多くの労力を費やしても、導入後に管理担当者や製造従事者の入れ替わりによって、継続的な運用が困難となることがあります。このような問題を解決するためには、従業員教育や無理のない仕組み作りが重要です。
例えば、取引先からHACCPの認証を取得するように言われたが、何から手をつければいいか分からない等、HACCP導入にあたっての課題や問題を一緒に解決いたします。
食品の「安全・安心」に関する検査、
支援実績の豊富な専門知識を
持った
プロフェッショナルが、事業者様の
問題解決のサポートをします。
\詳しく知りたい方は/
お問い合わせはコチラから
皆様の「お困りごと」を丁寧にヒアリングさせていただき、客観的に課題を洗い出します。その上で、課題解決につながる道筋をご提案いたします。また、継続的な運用や無理のない仕組み作りのための従業員教育として、座学をはじめ、ワークショップ形式、現場でのOJT方式等、ご要望に応じた対応が可能です。

当センターは、食品分野以外にも、水道や生活環境、自然環境分野での専門がいるため、総合的なサポートが可能です。例えば、水質検査や貯水槽管理、工場排水の検査など、いずれも法的規制がありますが、状況に応じた対応が可能です。

認証取得、仕組みの導入だけではなく、当センターでは、微生物検査や理化学検査も行っており、科学的根拠を基にした助言、改善提案が可能です。精度の高いPDCAサイクル(P:計画、D:実行、C:確認/評価、A:改善)を通して、業務を継続的に改善しながら、仕組み作りができるよう、サポートいたします。
HACCPに沿った衛生管理の実施にあたって、事業の規模や内容に応じて、2つの基準に分かれます。いずれも事業に応じた衛生管理計画の作成から実施改善が求められます。弊社では、お客様の事業に応じた最適で継続的な運用につながる仕組みづくりをご提案いたします。
食品衛生上の危害の発生を防止するために
特に重要な工程を管理するための取組

※写真はイメージです
取り扱う食品の特性等に応じた取組
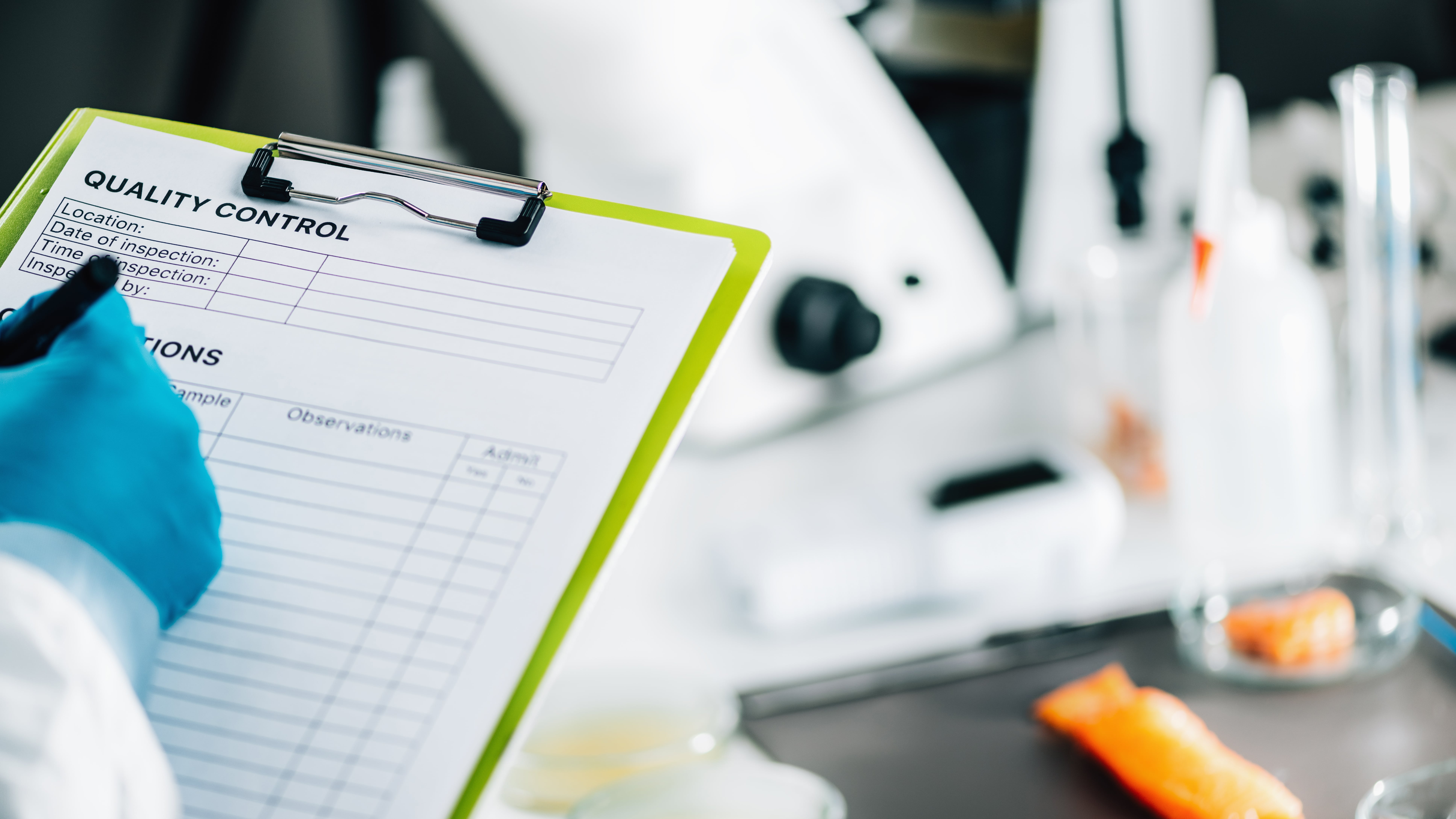
※写真はイメージです
弊社でサポートした実績をご紹介いたします。
STEP01まずはご相談
STEP02現状確認
STEP03お見積り・ご提案
STEP04ご契約
STEP05支援開始(指導)
水産食品加工施設HACCP認定制度は一般的なHACCP認証とは違うのか
水産食品加工施設HACCP認定制度は、水産物、水産加工品、水産食品に特化した認定制度です。水産食品加工施設HACCP認定制度についての詳細は、こちら。
食品を取り扱うにあたり、どのような認証をとるのがベストなのか?
お客様の認証取得の目的や取り扱う食品にもよるため、一概にはいえませんが、JFS規格は日本のあらゆる食品事業者が取り組みやすいように構成されており、ISO22000のような世界基準の規格との整合性が確保されています。また、「日本発」の規格であることから、規格要求事項の原文は日本語で理解し易いため、特に日本の中小企業などが取り組みやすくなっています。
HACCP認証取得にあたっての価格を教えてください。
申し訳ございません。当社ではお客様へのヒアリングや現場訪問をとおして事業所に応じたご提案を行っております。そのため一概に価格をお伝えできないためご了承ください。
HACCP認証取得までの期間はどれくらいでしょうか?
先ずは現場確認・把握を行ったうえで、お客様ご希望の期間も考慮しながら、サポートさせていただきます。
HACCPの義務化にあたって、何から取り組めばいいのでしょうか。
当センターでは、お客様の抱える困りごとに対して、客観的な視点からそれぞれの事業所に応じた仕組みをご提案させていただきます。
\詳しく知りたい方は/
お問い合わせはコチラから